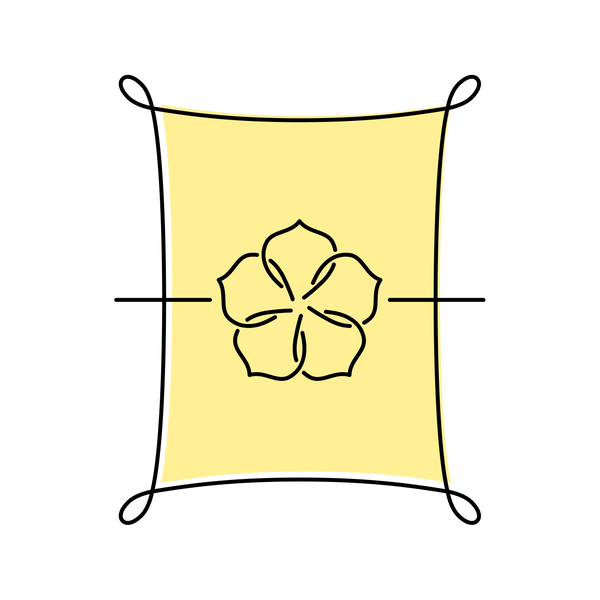お寿司のシャリのちがい 赤シャリとは?
お寿司を食べるとき、シャリ(酢飯)に注目したことはありますか?ネタの味だけでなく、お寿司の味はシャリの風味によって大きく左右されます。
シャリは大きく分けて関西風と江戸前風がありますがその違いをご存じでしょうか。
関西風のシャリの特徴

米酢をベースに砂糖を多めに加えた甘めのシャリで、多くの日本人にとって酢飯としてなじみがあるのはこちらの関西風の味付けではないでしょうか。酢の酸味は控えめで、ほんのりとした甘さとまろやかさが特徴で、みりんが使われる場合もあります。シャリだけを食べても甘みと旨味が十分に感じられるように味付けされています。
錦糸玉子や煮穴子、甘酢蓮根など調理済みの具材が使われることが一般的な関西風の寿司。具材の味付けも甘辛く炊いたものや甘酢を使っているものなどが多く、甘みがあるシャリでこそ味の調和が取れ全体のバランスが良くなります。
東西の寿司のちがいについてはこちらのコラムをご覧ください
また、押し寿司や箱寿司といった寿司の形が発展してきたため、しっかりと形を整えられるように米をやや硬めに炊くことも多いのが特徴です。
江戸前風の赤シャリの特徴

一方、江戸前寿司は江戸時代の東京湾(江戸前)で獲れた魚を生魚を酢で締めたり、醤油漬けにしたりするなど、保存・加工しながら提供する文化から始まりました。
そこで用いられたのが、赤酢を使ったシャリ、いわゆる「赤シャリ」です。赤酢とは熟成した酒粕を原料にして作られる酢で、米酢よりも色が濃く、独特の旨味とまろやかな酸味があります。
赤シャリは赤酢と塩が基本で、砂糖をほとんど加えないため甘みは控えめで、赤酢由来の深みのある酸味が際立ち、シャリの色も褐色気味になります。酢の利いたシャリは、シャリの酸味とネタの組み合わせが絶妙で、江戸前寿司においてシャリはネタの味を引き立てる役割を果たします。
赤酢は米酢が高価であった江戸時代に開発されたという背景もあり、米酢が安価に生産できるようになった現在では米酢を使う関西風が主流となりましたが、江戸前寿司の店では赤シャリを用いて寿司を提供する店も多くあります。
寿司の具材にあわせ、シャリもお好みで
関西風のシャリと江戸前の赤シャリ、それぞれ発展してきた背景によって違いが生まれました。ちらし寿司は関西風の寿司ですが、赤シャリを使ってはいけない、という決まりがあるわけではありません。好みによってぜひ両方のシャリを楽しんでみてください。
また、旅行や食べ歩きの際には、シャリに注目してみると寿司文化の奥深さをより楽しめるかもしれませんね。

ちらし寿司の具を中に入れ、玉子で包むことでワンハンドサイズに仕立てた「手づつみちらし」。ご家庭でのハレの日に食卓に並べ、ご家族そろって味わっていただければ幸いです。