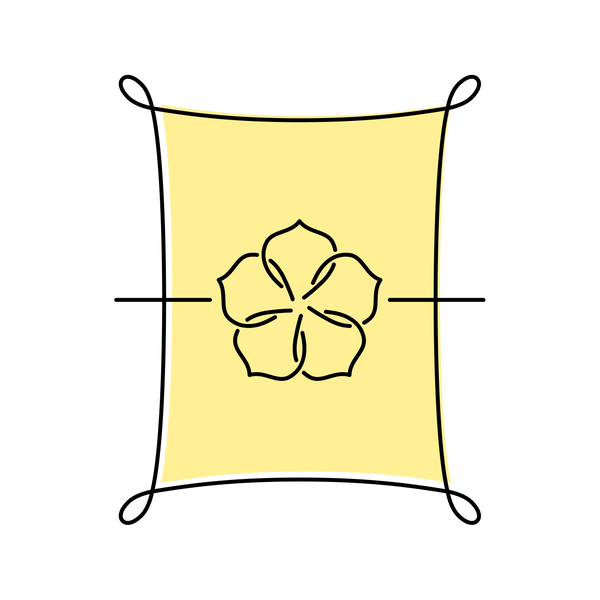種類は様々!東西で異なるちらし寿司
ちらし寿司というと、どういったお寿司のイメージを持ちますか?酢飯の上に錦糸玉子やゆでた海老や甘酢蓮根などの具材が散らされたものでしょうか。生のまぐろや海老など海鮮がのったものでしょうか。
ちらし寿司はお寿司の中でも家庭で作ることも多い身近なものですが、その種類は色々とあり、地域によってもイメージするちらし寿司に違いがあるのをご存じでしょうか。代表的なちらし寿司の種類や違いを紹介します。
ちらし寿司の由来と発展についてはこちらで紹介しています
西日本型(「ばら寿司」「五目寿司」)

酢飯に煮た干瓢や椎茸、人参などを混ぜ込み、錦糸玉子や海苔の細切りを散らして仕上げるスタイル。煮穴子や茹で海老、甘酢蓮根などの具材をのせる場合も多く、素朴でありながらも具だくさんで見た目の華やかさがあります。家庭料理として身近であり、祝い事や行事のハレの日の食事として長く親しまれてきました。
地域によっても特徴があり、酢しめの魚や野菜など具材が大きく品目数が多い「岡山ばら寿司」、辛く煮付けたサバを細かくほぐしたおぼろを散らした京丹後の「丹後ばらずし」などが有名です。
東日本型(「江戸前ちらし」「海鮮ちらし」)

酢飯の上に海鮮や厚焼き玉子などを美しく並べた華やかな盛り付けが特徴。握り寿司を作る際に余った切れ端をのせた、寿司職人たちのまかない飯から生まれたとされています。
この違いは、単に地域性だけでなく、食材の流通や保存技術、文化的な背景があります。
東日本の新鮮な魚介類を楽しむスタイルは、江戸時代に握り寿司が食べられ始めた頃にできたもので、西日本の乾物や煮物などを中心にした保存性の高い具材が使われるスタイルは生魚を新鮮に味わう文化が生まれる前のお寿司の形が基になっています。
形は自由、ちょっと特別なシーンにたのしむ身近なお寿司

最近ではアボカドやサーモン、ローストビーフなど様々な具材をトッピングするちらし寿司やケーキのようにデコレーションしたちらし寿司も見かけるようになりました。
形は様々でも、お祝いの席を華やかにしてくれる役割は共通していますね。
京都・二条城東に店を構える桔梗寿司のちらし寿司は、関西風の甘いシャリに甘辛く炊いた椎茸の中具をあわせ、たっぷりの錦糸玉子を載せているのが特徴。
「手づつみちらし」は、ちらし寿司の具を中に入れ、玉子で包むことでワンハンドサイズで食べやすく、可愛らしい俵型に仕立てた商品です。ご家庭でお祝いや特別な日の食卓に並べ、ご家族で味わっていただければ幸いです。