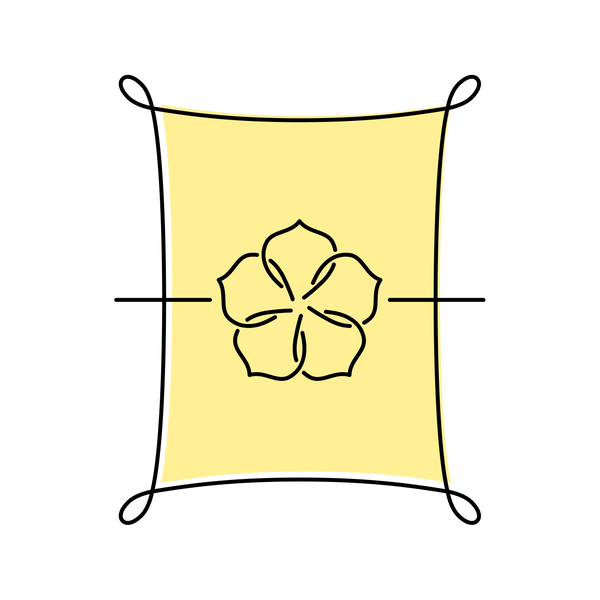ハレの日の定番、ちらし寿司の由来と発展
ちらし寿司は、日本人にとって非常に親しみ深い料理のひとつ。ひな祭りなどお祝いの席に欠かせない存在であり、様々な具材が鮮やかな見た目で「ハレの日の料理」として定着しています。
現代では様々な食材をのせたちらし寿司が登場していますが、ちらし寿司はどのように発展してきたのでしょうか。ちらし寿司の起源ははっきりしていませんが、その由来と発展について有力な諸説を紹介します。
東西のちらし寿司の違いについてはこちらで紹介しています
鎌倉時代に端を発する「混ぜずし」

ちらし寿司の最も古い形は、鎌倉時代にさかのぼると言われています。当時は酢飯に干瓢や椎茸などの具材を混ぜ込んだ「五目ずし」「混ぜずし」に近いものでした。
江戸時代終わり頃の三都(京都・大坂・江戸)の風俗などを記した書物「守貞漫稿」には、「ちらし五目鮓」の作り方が載っており、少なくとも、江戸時代末期には広く全国的に作られていたと考えられます。
「守貞漫稿」によると、19世紀後半の寿司屋の多くは握り寿司が主流であったと記されています。その一方で、当時の握り寿司は現代のものよりも大きく、ほおばる必要があったため、箸を使って食べるちらし寿司は品のよい寿司として女性に人気でした。また、きれいに詰められたちらし寿司は大名家族にも人気を誇り、明治の初めには、ちらし寿司の上に家紋を切り抜いた笹の葉を乗せた高級ちらし寿司が存在したこともわかっています。
岡山藩の「ばら寿司」

ちらし寿司の歴史を語る上で有力なのが、岡山藩の「ばら寿司」の逸話です。江戸時代、岡山藩主・池田光政は質素倹約を奨励し、庶民に「一汁一菜」の生活を命じました。反発した庶民が、魚や野菜をご飯に混ぜ込み、「一菜」に見せかける料理として誕生したのが「ばら寿司」です。入れられる具材は酢でしめたさわらや穴子、海老のほか、竹の子やごぼうを入れることも。具材が大きく品目数が多いのも特徴です。
岡山では「隠し寿司」「岡山ばら寿司」「まつり寿司」など地域や世代によって様々な呼び名がありますが、今でも郷土料理として親しまれています。
江戸時代後期の「江戸前ちらし寿司」

現在よく知られている生の魚を酢飯の上に美しく並べるスタイルは、江戸時代に、今の「握り寿司」が食べられ始めた頃にできたもので、握り寿司を作る際に余った切れ端をのせた、寿司職人たちのまかない飯から生まれたとされています。
忙しい職人が余った刺身や具材を酢飯の上に手早く盛りつけて食べる簡便な料理が、そのまま客にも提供されるようになり、「江戸前ちらし寿司」として広まっていったのです。
ハレの日に彩りを添える、ちらし寿司

一言にちらし寿司といっても、様々な形があるお寿司の中でも自由度が高いちらし寿司。スタイルは幅広いですが、いずれも見た目が華やかでハレの日にぴったりですね。
京都・二条城東に店を構える桔梗寿司のちらし寿司は、関西風の甘いシャリに甘辛く炊いた椎茸の中具をあわせ、手焼き・手切りの錦糸玉子をたっぷりと載せた京風のちらし寿司。
「手づつみちらし」は、そのちらし寿司を味はそのままに、具を中に入れて玉子で包むことでワンハンドサイズで食べやすく、可愛らしい俵型に仕立てた商品です。ハレの日に食卓に並べ、にぎやかにたのしんでいただければ幸いです。