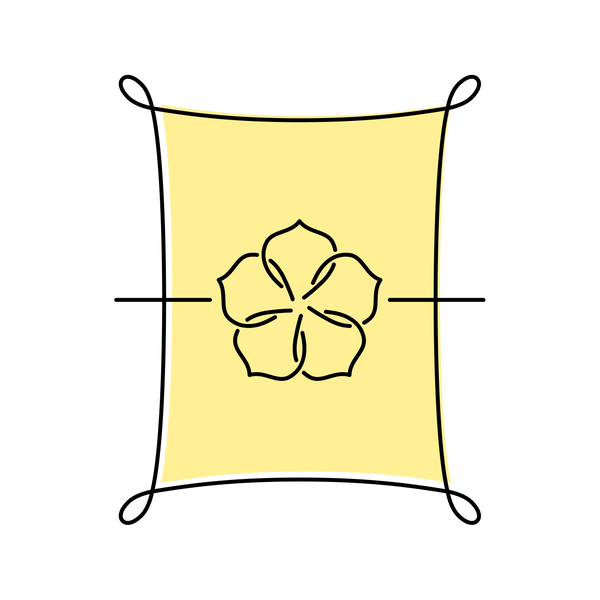こどもの日の由来と行事食 なぜちまきとかしわ餅?
男の子の健やかな成長を祈願する「こどもの日」。五節句のひとつ「端午(たんご)の節句」が起源です。
節句とは?
節句とは季節の変わり目に邪気を払うために、無病息災などを願って行われていた中国の風習で、日本に伝わり季節行事として根付いてきました。たくさんの節句があったなかで、江戸幕府が下記の5つの節句を公的な祝日として定めたことから、特に「五節句」と呼ばれるようになりました。
- 1月7日:人日(じんじつ)の節句…七草の節句
- 3月3日:上巳(じょうし)の節句…桃の節句
- 5月5日:端午(たんご)の節句…菖蒲の節句
- 7月7日:七夕(しちせき)の節句…笹竹の節句
- 9月9日:重陽(ちょうよう)の節句…菊の節句
それぞれの節句では、旬の食材や邪気を払うとされる食材を使った食材を食べる習わしがあります。1月7日が「人日の節句」ということはあまり知られていませんが、その一年を健康に過ごすことを願って七草粥を食べる習慣はご存じではないでしょうか。
「端午の節句」がこどもの日の起源

「端午の節句」は春秋戦国時代の中国の故事を起源とする病気や災厄を避ける行事が日本に伝わったもの。「端午(たんご)」は旧暦において「初め」を意味する「端」の「午(うま)の日」である月の初めの午の日でしたが、現在は5月5日となっています。
5月5日が「こどもの日」として法律で祝日として制定されてからは、子ども全員を祝うのが一般的となりました。「国民の祝日に関する法律」によると「男女問わず、すべての子どもの幸福を願い、母に感謝する」日であると定められており、子どもの成長だけでなくその母親への感謝をする日でもあります。
こどもの日の行事食

こどもの日には五月人形を飾ったり、勝負事に強くなるように菖蒲湯に入ったりと縁起を担ぐ風習がありますが、行事食としてはちまきとかしわ餅があります。
ちまきを食べる風習は、中国から伝わったもの。中国では春秋戦国時代の故事に起源を持つ言い伝えからちまきは「忠誠心が高い象徴」として考えられています。そのため、 忠義のある子に育つことを願い、ちまきを食べるようになりました。ちまきを食べる風習は、風習が伝わった当時の都があった関西・近畿を中心に西日本へ広がりました。
かしわ餅を食べる風習は江戸時代に日本で生まれまたと言われています。柏は、冬になっても葉を付けたまま過ごし、新芽が吹く頃に落葉する特徴があります。後継ぎができるまで葉を落とさないため、縁起担ぎのめでたい木と言われ、そこから「家(家系)が途絶えないように」という願いを込めて神事に欠かせない餅を縁起の良い柏の葉で包んだ柏餅を端午の節句に食べることにより、 男の子が元気に育つことを願って始められたといわれています。
桔梗寿司の「手づつみちらし」も、それぞれ縁起物の具材を使いっており、お祝い事の行事食としてもぴったり。ハレの日に食卓に並べ、にぎやかにたのしんでいただければ幸いです。
京都・二条城東に店を構える桔梗寿司のちらし寿司は、関西風の甘いシャリに甘辛く炊いた椎茸の中具をあわせ、たっぷりの錦糸玉子を載せているのが特徴。
「手づつみちらし」は、ちらし寿司の具を中に入れ、玉子で包むことでワンハンドサイズで食べやすく、可愛らしい俵型に仕立てた商品です。ご家庭でお祝いや特別な日の食卓に並べ、ご家族で味わっていただければ幸いです。